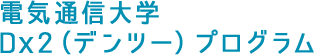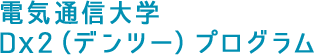2024年度D×2プログラム修了生

(おおぎし まゆ)

(やまぐち れんと)

(やまさき ちひろ)

(とくたけ ゆう)

(いのうえ あゆか)
インタビュアー

原田 慧 先生
電気通信大学・教授。企業でのデータ分析やデータサイエンティストのマネジメントなどを経験した実務家教員。D×2プログラムの推進役。
ブートキャンプ(集中講義形式の実践演習)について

——D×2プログラムの特徴として「デザイン思考」があり、それを体得する場としてブートキャンプ(集中講義形式の実践演習)をやっています。これは初めての取り組みなので私も手探りでしたが、参加してみてどうでしたか?
山口:僕自身がかなりエンジニア気質というか、何かを作っている工程に面白さを感じるタイプなので、デザイン思考の実習で取り組んだように、事前に受け取り手をイメージして「作るべきものを作る、作らなくていいものは作らない」という思考は常に忘れてはいけないな、と思いました。言葉にすると当たり前だけど、案外できていない人は多いんじゃないかと思います。
井上:初めての経験だったので難しいことも多かったけど、実際に何かを生み出すことの楽しさを感じることができたと思います。
徳武:上流から下流までを気軽に体験できる良い講義でした。コマ数の関係上難しいとは思いますが、一旦作るところで終わってしまったので、成果物を実際に使用してもらってフィードバックを得るという経験もしてみたかったですね。
山﨑:LLM(大規模言語モデル)を使ったプロダクト開発のブートキャンプが印象に残っていて、今までそのような開発経験がなかったのですが、「どのようなものを作ると嬉しいか」という要件定義→学生間でブラッシュアップ→コードにおこすという流れを経験してとても面白かったです。その後も研究室にこういうのあったら嬉しいよねと考えて作ってみるようになりました。
——大岸さんは学部生の頃からハッカソンなどにたくさん参加して慣れていますよね?
大岸:そうですね。自分で何かを作ることは元々好きでした。それでもブートキャンプを通じてユーザの視点から物事を考えることの大切さを学んだと思います。LLM(API)を用いてアプリケーションを作ったのは初めての体験で、開発するだけではなくデータサイエンスの知識も活かせて良かったです。学生にとってはAPIの料金も小さくはないので、そういう点もありがたいと思いました。学外の優秀なエンジニア(ブートキャンプのゲスト講師や参加者)と関わることができたのもよかったと思います。
——デザイン思考の実習で、皆さんに伝えたかったことが伝わっていたようで安心しました。
ブートキャンプの様子
Kaggleについて

——D×2プログラムのもう1つのDである「データサイエンス」の方では、Kaggle を取り入れた講義(必修ではない)が特徴的です。山口くんはつい最近私と一緒にコンペティションに出たところですね。
山口:Kaggle には、原田先生の講義で興味を持ったことがきっかけで取り組み、2年間で3つのメダルを獲得でき Kaggle Competition Expert になりました。中高大と今までの教育において、自分は綺麗に整備された問題に対して、知っている知識を当てはめて解く経験はありましたが、Kaggle をはじめてからはデータの収集元や性質を深く見て、比較的実務に近いような分析を行う力がついたと思います。チームで知識を共有して高め合う経験はなかなか味わえないので、まずは Kaggle から気軽にやってみるといいと思います。在学中に Master になりたかった!!
——金メダルが取れたので Master は時間の問題ですね。
徳武:D×2プログラムは原田先生を始め実績豊富な方が多く、声をかければ一緒に参加したいという人も多い印象です。また、Google Cloud などの計算資源が利用できるため、気軽に挑戦しやすい環境が整っていました。
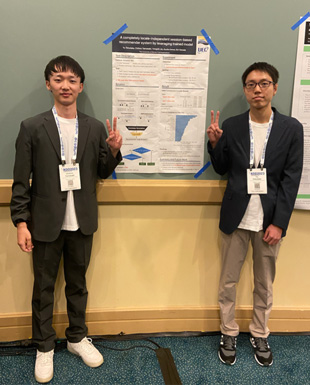
——徳武くんはKaggleだけではなくて、KDDやRecSysのコンペティションに出ていますね。
徳武:国際会議の付帯コンペティションでは、入賞すれば論文を執筆し、会議で発表する機会を得ることができます。さらに、トップ会議に採択された最新の研究発表を聴講できるため、自身の研究アイデアを広げる良い機会にもなります。挑戦するメリットが多く、とてもおすすめです。
——純粋な競技だと研究になりませんが、こういう形で研究につながるのはとても良いことですね。
大岸:私は元々興味はあったのですが、このプログラムに参加してからデータサイエンスの面白さに気づき、コンペティションやデータサイエンスのサークルにも参加するようになりました。インターン期間中に山﨑くんと徳武くんと一緒にSIGNATEの画像分類コンペティションに取り組めたのは良い思い出です。
——この2年間を改めて振り返ってみてどうでしょう?
山口:間違いなく自分の行動力と将来を変えたと思います。「少しでも気になれば飛び込んでみる」だったり、「とりあえず先人等の話を聞いてみる」は確実に自分の行動指針になっているし、以前までは持ち得ていなかった。これらは、D×2プログラムとして明示的に教えられたわけではないけど、2年間を通じて与えられた多くの機会は、自分の意思で選択する力を付けるのに役立ったなと感じます。
大岸:海外インターンシップなど、普通のプログラムと比べてしなければいけないことが多くて面倒だと思う人もいるかもしれないけど、このプログラムに入ったことで普通ではできない経験ができました。このプログラムに入って本当によかったです。
徳武:コンテンツも特徴的ですが、個々人が主体的に動き、考えることが求められる点が特徴的だと感じています。私自身、それまで主体性を発揮することがあまり得意ではありませんでしたが、この環境を通じて、技術面だけでなく人間的にも大きく成長できたと実感しています。
井上:D×2プログラムの面白い同期や先生方に出会えたことがよかったと思っています。私は外部の大学から大学院進学の時に電通大に来たので研究室以外で知り合いができてよかったし、自分と同じようにD×2プログラムに飛び込んできた仲間から刺激を受けることは多かったです。
徳武:大学院の研究室所属だけではどうしても交友関係が狭くなってしまうので、別の研究室の山口くんや大岸さんを始め、大学院に入ってからバックグラウンドの違う学生や先生方と出会えたのは良かったかなと思います。
山﨑:プログラム内での交流が多く、サークルのようなプログラムという印象があります。交友関係が広がるのはもちろん、他の人から色々な知識を得られたり刺激を受けることが多かったと思います。
山口:月並みですが、多くの人と関わっておくと良いことがあるな、と思います。プログラム内で興味を持ったことがきっかけで、外部の人と話をする機会が多くなりました。
——最後に後輩に向けて一言お願いします!
山口:面白いプログラムだからこそ面白い人たちが集まっていると思います。今後もぜひ面白くなり続けてほしいです。
山﨑:先生方や在学生からもプログラムをもっと良くしていきたいという思いがひしひしと伝わってくるので、これからどんどん発展していくと思っています! 最近所属された学部1年生の方達が今後どのようなことを学んでいくのか楽しみに応援してます。
——ありがとうございました。私たちもこれからの皆さんの活躍を楽しみにしています!